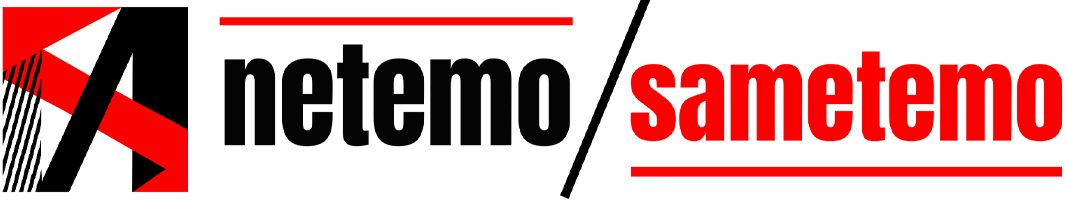伝説の迷作『Anthem』の舞台裏が語られる。元リードプロデューサーが明かす「飛行」システムの明暗

エレクトロニック・アーツ(EA)傘下のBioWareが2019年に発売したオンラインアクションRPG『Anthem』は、華々しい期待を背負いながらも、最終的には不完全な形でリリースされ、多くの批判を浴びたタイトルだ。発売からわずか数年後には大型アップデート計画「Anthem NEXT」も頓挫し、2026年1月にはサーバー閉鎖が予定されている。
そんな中、同作の元リードプロデューサーであるマーク・ダラ(Mark Darrah)氏が、自身のYouTubeチャンネルで公開したドキュメンタリー動画シリーズ「What Happened on Anthem」で、当時の開発状況を赤裸々に語ったことで再び注目が集まり、海外メディアを中心に「飛行」システムが抱えた光と影について報じられている。
今回の映像でダラ氏が特に強調したのは、『Anthem』の最大の特徴でもあった「ジャベリンの飛行システム」だ。一見するとゲームの象徴であり、プレイヤー体験を強く印象づける要素であるが、その裏側には開発チームの機能不全と意思決定の迷走が如実に表れていたという。
2017年、BioWareの看板的存在であるケイシー・ハドソン氏が一時的にスタジオを離れたことで、『Anthem』の開発は明確な指針を失った。ダラ氏によれば、この時期のチームでは「決断が遅れる」「決定が覆される」「誰も責任を取らない」といった悪循環が蔓延し、プロジェクトが一向に形にならなかったという。
典型的な例がミッションデザインだ。本来であれば複数のプロトタイプを並行して検証し、手応えのある仕組みを見極めていくべきところ、実際には「Den of Wolves」と呼ばれる1つのミッションに執着し、何度も作り直すばかりで前進がなかった。これにより、開発後期になってもゲーム全体の体験像が固まらず、結果として発売直前まで基盤が揺らいだまま進行することになったとのことだ。

また、拠点間の不信感とコミュニケーション不全も深刻な問題だったようだ。BioWareはカナダ・エドモントンとアメリカ・オースティンに開発拠点を構えていた。しかし、エドモントン側がオースティンの成果物に対して不信感を抱き、現場の状況が十分に理解されないまま判断が下されることも多かった。
後にオースティン側がシニアプロデューサーやテクニカルリードを担うようになり、ようやくチーム間の連携が改善に向かったものの、時すでに遅し。根本的な問題は開発後期には修正困難となっており、結果的にチーム全体の士気を下げる要因となった。

そして、本作の大きな特徴だった「飛行」についてもゲームの完成度に大きな影響を及ぼすことになったようだ。『Anthem』の代名詞ともいえる「飛行」システムは、プレイヤーに圧倒的な自由度を与え、発売当初から「唯一無二の楽しさ」として高く評価された。しかしダラ氏は、これこそがプロジェクトの構造的欠陥を象徴する存在だったと語る。
飛行は開発初期から導入されていたが、その後「削除→再導入」を何度も繰り返した。そのたびに設計全体が揺さぶられ、最終的には中途半端な形でゲームに組み込まれることとなった。
一時は「飛行を外してコアデザインに集中し、後から再導入する」という判断がなされた。しかし、飛行を外した前提で設計された要素は、再び飛行を組み込む段階で整合性が取れなくなり、ゲーム全体の歪みとして残ってしまった。ダラ氏は「飛行は『Anthem』における最高の特徴であり、同時に最悪の特徴でもある」と締めくくっている。
紆余曲折ありながらも発売まで漕ぎつけた『Anthem』だが、リリース後の評価については話すまでもないだろう。また、ダラ氏によると、本作の危機感の欠如は発売直前まで続いていたようだ。
『Anthem』の問題は開発中から内部で指摘されていた。エンドゲームコンテンツの不足、経済システムの不備、繰り返し感の強いミッション構成など、これらはチーム内で共有されていた課題だったにもかかわらず、明確な対応策が打たれないまま発売を迎えたとのこと。
このほかにも、多くの問題が「最後の数か月」で表面化し、修正する時間はほとんど残されていなかったと話している。結果として、プレイヤーに提供されたのは未完成感の強い製品であり、ローンチ直後から厳しい評価にさらされる結果となった。
2017年の動画公開以降、そのビジュアルと「飛行」という大きな特徴から高い注目を集めた本作。その期待値の高さ故に製品版の完成度に対する落胆の声も非常に大きかった。『Anthem』は2026年1月にサーバーが閉鎖され、完全にその幕を下ろす。
しかし、ダラ氏の回顧録はただの失敗談ではない。大規模ゲーム開発におけるリーダーシップ、意思決定、そして一貫したビジョンの重要性を改めて示すケーススタディとして、今後も語り継がれるだろう。